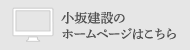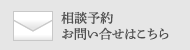石場建て構法 #1正しい選択 |
伝統構法と耐震性能, 伝統構法について |
石場建て構法は、日本の建築史上もっとも耐震性能のすぐれた構法であることは、まちがいありません。
この構法で建てるには、残念ながら、基準法上のネックとなる点が、幾つかあり、建てることが困難にされてしまっています。
この点についてはまたの機会にゆずるとして、まずは、石場建てとはどんな構法なのか、感覚的にこの構法をとらえてみるのが、わかりやすいです。
まず、この構法には、コンクリートの基礎がありません。
地面を突き固め、独立した礎石の上に柱を建てます。この礎石が基礎です。
基礎に求められる、本来の性能とはなんでしょうか。
コンクリートの耐用年数はざっと50~60年程度です。
木は、100年以上持ちます。材をえらべば200~300年、それ以上もたせることも可能です。
石の耐用年数は、数百年~数千年。 普通に考えれば、基礎は、耐用年数が、一番長いものを選ぶのが、正しい選択ではないでしょうか。
人は本来、正しい選択を理屈ではなく、感覚で選択できる能力を持っています。
理屈はわからないけれど、なんとなくこっちの方がよさそうといった感覚です。
特に女性の方が、男性より、この感覚の点は優れていると思います。
話しが横道にそれてしまいました。基準法では、コンクリートの強度ばかりが取り上げられ、耐用年数には目が向いていません。コンクリートの基礎の上にのっている長期住宅など、あり得ない話しなのです。
結局、強度という言葉が、あまりにも多くの勘違いを、生んでしまっている様に思います。
もともと私達は、コンクリートに頼らずとも、金物に頼らずとも、長期にわたって、地震に耐えうる家づくりが出来ていたのだから、素直にその作り方を受継げばいい。そこに何んの心配もありません。
明治維新で、西洋の建築技術が導入され、木造建築に筋かいを入れることに、当時の大工たちは、ものすごく抵抗したと聞き、心が熱くなりました。
レンガとセメントしか知らない者に、木の何がわかる。そういう口惜しさだったのでしょう。
阪神淡路大震災、宮城県沖地震、新潟県中越沖地震、幾つもの極限状況を経て、立ち続けている古民家の存在に、ようやく国も見直しを始めました。 これも正しい選択のひとつです。
関連ホームページ
「伝統構法でつくる家」
「日本本来の家づくり」