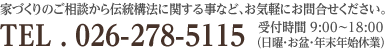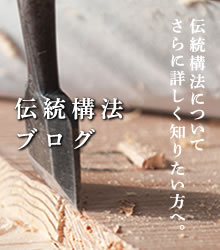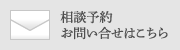- 一言(7)
- 伝統構法の家(79)
- 土壁・漆喰の家(1)
- 小柴見M様邸
- 篠ノ井T様邸(1)
相談予約・お問い合せはお電話または、フォームから承っています。
石場建てと免震構造
熊本の震災でおきた家屋の倒壊は、これまでの地震の被害状況と少し状況が違っていて、短時間に大きな揺れを複数回受けたことによる倒壊が特徴としてあります。
1回目の揺れには耐えられたけれど、2回目で倒壊に及んだということでした。しかしこれは予見できなかったことではありません。
以前から、今の一般的な家のつくりはどうなのかと、打ち合わせの度にお客様からよく聞かれてきました。
その都度お答えしたことは、今のつくりは1回目は持ちこたえることができても、2回目がきたらアウトですと答えてきました。
なぜそう答えられたかといいますと、以前、栄村の震災を現地で観察した時、築3年の最新の耐震基準で建てられた家の土台から通し柱が浮き上がり、土台と通し柱をつなぐホールダウン金物のビスによって通し柱が猫の爪で引き裂かれたようになっていました。
家は倒壊を免れていましたが、人間でいう足首が骨折した状態でかろうじて立っているようなものです。
この状態で2回目の大きな揺れがきたらとてももたない。
耐震、制震、免震と3つの作り方がありますが、今の家の構造はすべて地面と家を固定した上で、建物を固く作る耐震構造で造られています。
伝統構法に取り組む際、いろいろな大学の教授や構造の専門家の意見やお話しをきいてきました。
その中で概ね関東と関西に分類できることに気が付きました。
関東の先生がたは、往々にして金物を使って家を固くつくることに傾倒している印象をうけました。人の技術や知恵より剛構造による計算至上主義といったところです。
これに対し、関西の先生方は、柔構造のいまだ未知なる部分に対する研究心にあふれている印象をうけました。
人は知識に溺れる人ほど自分の目に見えないものに対する謙虚さを失いがちです。
知識がなくとも、普通になんの根拠もなく、単に感覚でこちらの方がいいよねと選択し、その結果、まさに正しい答えを選べる感性を人間は持っています。
千年以上たち続ける木造建築も、それを作った時代は、計算によって安全性を確かめた後で作ったのではありません。
それまで試行錯誤の結果から、こうして作っておけば長持ちするだろう、という大工の感性が超長寿命の建築を完成させました。
計算が先立って建物ができたのではない。
建物が先で、計算は建物性能のほんの一部を証明できるようにようやくなってきただけのことです。
地面に固定された、固い建物と、地面に置いてあるだけの柔らかい建物と、激しく揺れる地面に対してどちらが壊れにくいと思いますか?
この問いが、わざわざ計算をしなければならない難しい問題とは思えません。
奈良県にある、江戸時代に建てられた高木家(重要文化財指定)は、これまでマグニチュード7以上の地震を8回以上受けていまも建ちつづけている事。
東日本大震災でも岩手の古民家は普通に建ちつづけている事、熊本の震災でも伝統構法の建築は倒壊せず建ちつづけている事。
これらはすべて石場建て、いわゆる地面に置いてあるだけの免震構造です。
これは、理論や計算の話ではなく、設計思想の問題です。
どのような考えに基づいて建物をつくるのが良いのか。
名もない大工たちが受け継いできた知恵の集まりには、研究が進むほど、理にかない深く関心することばかりです。
木のしなり、復元力を最大限に生かした柔構造と、地面に固定せず置くだけの作り方。
これに対し、国の政策を主導してきた者たちは、木を、曲げ、せん断、圧縮でのみ評価し、木の本来のしなりや復元性能を軽んじた上に、あくまで地面に固定するつくりから離れようとしない。
こうした人たちは、強度に固執します。そのため大工の仕口より金物の方が信頼できるとしています。
しかし、柔構造と免震構造においては金物ほどの強度はそもそも必要ありません。
家のつくりというものは、強度のみで比較判断するのがそもそもの間違いで、長期間耐力を維持するために木材にもっともストレスを与えないつくりを考えることが正しい作りとなります。
木は金物で固定するのではなく、木は木でつなぐのが正しい。
木材を生き物として扱うのが本来の日本建築の思想であって、木を鉄と同じにみなし、金物固定に安心を求める思想はどっかずれてるとしか思えません。
木は正しい作りをすれば、金物を凌駕する。
私は、知識は恥ずかしいほどしか持っていませんが、正しい選択ができる感性だけは見失わないようにしたいと常々思っています。